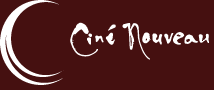|
1936年に何があった?と訊かれても、一瞬、?となるかもしれない。でも、昭和11年だよ、と言われれば、そうだ、二・二六事件があったとなるだろう。やがて戦争に到るきな臭さが漂い始めた年だ。だが、この年は、そんな世相にも拘らず、日本映画に数々の傑作が生まれていたのだ。「2024優秀映画鑑賞会」では、溝口健二の『浪華悲歌』が上映されるが、溝口は同年、続けて『祇園の姉妹』を撮り、小品ながら、同じ山田五十鈴主演で『お嬢お吉』も作っている。清水宏の『風の中の子供』は翌年だが、36年には、日本ヌーベルバーグの嚆矢ともいうべき快作『有りがたうさん』を撮っている。
では、小津安二郎はどうか? 彼のトーキー第一作『一人息子』を撮っている。出世を期待した息子の東京での侘しい暮らしぶりに落胆しつつも、彼の優しさに慰められる母。小津や清水より2歳下の成瀬巳喜男の傑作『妻よ薔薇のやうに』は35年だが、36年には、『桃中軒雲右衛門』がある。このほか、挙げればキリもないが、1930年代半ばは、日本映画の黄金期だったのだ。そのなかで、溝口は、『浪華悲歌』で、世の蔑みや家庭の団欒に背を向け、一人決然と我が道を行く女を輝かせ、戦後の『山椒大夫』では、兄を助けるため入水する香川京子の安寿に光を当てた。
今回の二本柱は、溝口健二と清水宏だが、この両者は、対照的だと思う。溝口は、あくまでも劇の作家なのだ。劇とは、たんなる物語ではない。ベースとしての物語を、劇的空間へと高め、そこに生きる人間を輝かせるのだ。対する清水宏は、どうか?物語を、現にある世界へと解き放ち、そこに息づく人間を捉えるのだ。『風の中の子供』の、ターザンの真似事をする少年を見よ。戦災孤児と共同生活を営み、自主製作で撮った『蜂の巣の子供たち』三部作における子供たちの、いとも自然な姿。それをカメラを通して捉えるのには、揺れ動く生を掬い取る清水の卓越した眼が働いているのだ。
|
|