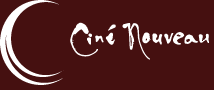|
橋本忍という脚本家の存在を意識するようになったのは、どの作品からだったろう? イヤ、それと知らずに、彼の脚本による映画は、いろいろ見ていた。黒澤明監督の『七人の侍』はむろん、今井正監督の『真昼の暗黒』にしろ、中学生の時に見ているのだ。とくに『真昼の暗黒』は、八海事件を扱った映画だということを、中坊なりに聞き知って、従兄と一緒に見た。印象は強烈だった。所々、笑える場面があるものの、警察から犯人扱いされることの恐ろしさを、ガキなりに身に沁みて感じたのである。でも、それが、橋本忍の綿密な取材に基づく脚本に支えられてのものだとは考え及ばなかった。
今回のシネ・ヌーヴォの特集で上映する橋本忍脚本作品では、1951年の『平手造酒』や、同54年の『初姿丑松格子』は見ていないが、あとはだいたい見ている。だが、わたしが映画を観て、この脚本を書いたのは誰だろうと興味を持ったのは、小林正樹監督の『切腹』だった。というのも、主人公がここに到った経緯を、回想に次ぐ回想で明かしていく構成に、目を見張ったからである。そこから、それ以前に見て、わたしが好きだった野村芳太郎監督の『張込み』や『ゼロの焦点』も、橋本忍の脚本だったことを知ったのである。以後、『砂の器』や『八甲田山』に到る作品については言うまでもない。
橋本忍脚本は、人が生きていくうえで、自身ではどうにもならない不条理な力に見舞われる悲劇が多い。ただ、それを見て、観客は涙を流しはしても、それで打ちひしがれるというのではなく、逆に、自分の人生を肯定するのではないか。そういう力があるからこそ、橋本忍作品は、多くの観客の支持を受けてきたのだろう。優れた脚本家は他にいても、一時代を画したのは橋本忍だけではないか。春日太一さんの労作『鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折』は、そのような橋本忍の脚本作りから、製作に向かう姿勢、さらには経営者としての才覚まで明らかにしているので、是非、ご一読を。
|
|