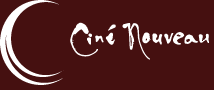|
わたしが、小津安二郎の作品を一番よく観ていたのは、1980年代の10年間、神奈川県の茅ヶ崎に住んでいたときだ。先住者の山根貞男さんが、市の公民館の職員から相談を受けたのをきっかけに、各所の公民館で「映画村」という映画上映会をやることになり、わたしも,その手伝いをしたのである。当時は、まだ、国のあちこちに16ミリの映画フィルムを貸し出す業者があったので、そこから、これぞと思う作品を借りだして上映したのだ。新旧取り混ぜた日本映画をやった中で、いつやっても、多くの人から、良かった、面白かったと言われたのが、小津安二郎の作品だった。
実際、小津映画は、何度観ても面白い。話の筋はわかっていても、観る度に、ホー、こんなふうに描かれていたのかと、新たに気づくところがあるのだ。それは、ちょっとしたセリフのやりとりであったり、人の出入りであったり、室内外の撮り方であったりするのだが、それが画面を豊かに弾ませるのである。『晩春』で、原節子の紀子が、花嫁衣装で父に挨拶をして階下に降りたあと、杉村春子は、部屋をぐるりと二度回る。何故か? そこに意味はない。にもかかわらず、画面は弾む。それが映画なのだ。物語を超えた映画ならではの豊かさ。小津安二郎は一貫してそれを追求したのである。
とはいえ、それは一筋道ではない。シネ・ヌーヴォの今回の特集には、戦前の作品が4本入っているが、『その夜の妻』を初めて観る人は、驚くのではないか。夜の街の撮り方や強盗の場面など、アメリカのフィルム・ノワールを思わせるからだ。小津がいかにアメリカ映画に親近していたかがわかる。『淑女は何を忘れたか』も、その気味がある。そこから小津は、庶民の暮らしを描くようになるが、それは戦後の二作にも続く。小津安二郎といえば、とかく『晩春』以後の作品が評価されるが、わたしは、それ以前の作品も大事だと思う。その流れは、わたしが好きな『東京暮色』などにも繋がっている。
|
|