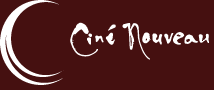|
笠置シヅ子と聞けば、「東京ブギウギ」とか、♪おっさんおっさん、わてほんまによう言わんわという歌詞が耳に残る「買物ブギー」などの歌と共に、彼女が踊っている姿が目に浮かぶ。といって、当時、6、7歳のガキだったわたしが、日劇などの舞台を見たはずもない。テレビもない時代だから、歌は、ラジオから流れるのを聞いていたかもしれないが、彼女の激しいパフォーマンスを記憶の底に残しているのは、映画の中で歌い踊るのを見たためかもしれない。たとえば、黒澤明の『酔いどれ天使』で、彼女が「ジャングル・ブギ」を歌うところで、暗い画面が一瞬、パッと明るくなる印象と共に。
わたしはNHKの朝ドラを見る習慣がないので、笠置シヅ子をモデルにしたという物語が、いま、どのあたりの話になっているか知らないが、宝塚音楽歌劇学校に、体格のせいで入れなかった彼女が、松竹歌劇養成校には、直談判で入学したあと、1938年に、生涯の音楽の師となる服部良一と出会って、ぐんぐん才能を伸ばしていったというのを後付けで知った。とりわけ、彼女が黒人娘に扮した『ラッパ娘』(1939)では、そのリズム感溢れるステージは、うるさ型の双葉十三郎や野口久光、南部圭之助などに絶賛されたという。彼女は、すでに戦前にスターとなっていたのだ。
だが、1941年の大東亜戦争の開始と共に、事態は暗転する。ジャズに才能を発揮する服部良一と、彼の作曲で生きる笠置シヅ子の歌や踊りは、「敵性音楽」として攻撃され、沈黙を強いられる。おそらく、その辛い経験が、彼らをして、日本の敗戦を機に、思い切り羽根を広げさせたのだ。わたしは、ブギウギの笠置シヅ子こそ、真に戦後を体現した歌手であり表現者だったと思う。三島由紀夫が、彼女を明治以来の三大女傑を継ぐと言うほど大ファンだったように、著名人のファンが多かったが、わたしは、当時、パンパンと呼ばれた街娼たちが、笠置の舞台に列を成したことに、彼女の栄光を見る。
|
|