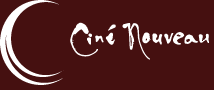|
世にスターと称される俳優は数多あれど、不世出の映画スターとなれば、市川雷蔵を措いてない。1954年、22歳で歌舞伎の舞台を離れて映画界入りし、1969年、わずか37歳で亡くなるまで、銀幕を輝かせた雷蔵。大映は、雷蔵を、長谷川一夫を継ぐ役者として育てようとしたようだが、『新・平家物語』(1955年)で演じた、若き日の平清盛で、「格調高い悲劇も鮮やかに演じる優れた役者になった」と評価され、一挙にスターダムにのる。以後、雷蔵は、彼ならではの時代劇スターとして活躍していくのだが、初めての現代劇『炎上』(1958年)において、新生面を開く。
『炎上』は、周知のように三島由紀夫の『金閣寺』が原作。雷蔵は、金閣寺に弟子入りした吃音で孤独な青年の屈折した想いを体現し、監督の市川崑をして、完璧!と言わせたのである。以後、数は少ないながら、現代劇でも、雷蔵ならではの孤独な青年像を体現して見せたことは、『破戒』(1962年)や『剣』(1964年)などの作品で明らかだ。では、本流の時代劇ではどうか。彼が、状況に強いられる悲劇を体現した屈指の作品といえば、『薄桜記』(1959年)であろう。そこでの悲劇性を、内に抱える虚無として現したのが『大菩薩峠』から『眠狂四郎』に到るシリーズである。
だが、悲劇的な美しさだけで雷蔵という役者を捉えるのは一面的だろう。彼には、『弁天小僧』(1958年)や『お嬢吉三』(1959年)のような、江戸のチンピラの軽みをみせる芸もあるのだから。スターの多くは、自分が得意とする役に拘る。だが、雷蔵は、変幻自在に多彩な劇を生きてみせた。その秘密は、彼が自分でしたメイキャップにあるようだ。普段着では、すれ違っても気づかないような普通人ふうの雷蔵が、メイキャップをしたとたん、その役が立ち現れたという。それは、彼が、常に役のイメージを的確に捉えていたということだが、それが彼を不世出のスターたらしめたのだ。 |
|