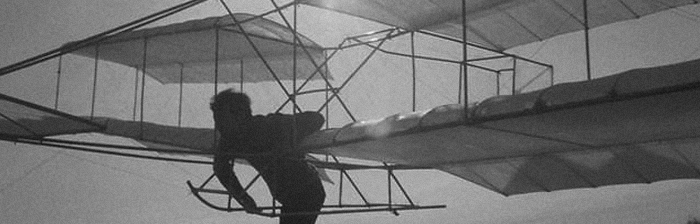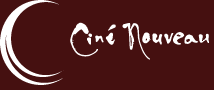|
寺山修司の名前を聞いて、真っ先に思い浮かぶのは、「マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや」という短歌だ。どうです? 口に出して詠み上げてごらんなさい。格好いいでしょ。ただ、この上の句は、他人の句を拝借してきたものなんだ。それで非難されたりもしたが、下の句が、見事に全体を生かして大きな佇まいを見せていることは確かだ。寺山は、このようなコラージュの天才なのだ。当時の若者たちに多大な影響を与えた『書を捨てよ、町に出よう』だって、アンドレ・ジッドから拝借したものだし。彼は、短歌のみならず、芝居も作詞や映画にもマルチな才能を発揮したが、ベースには、模倣による反復とずらしというコラージュ的手法がある。
それは、オリジナルという神話が崩壊した20世紀の芸術に通底する姿勢といっていいだろう。アンディ・ウォーホールのスープ缶やマリリン・モンローの画像にしても、模倣と反復によるずれに、新たな美を生み出したように。寺山は、日本では、まだそのような方向が定かでなかった時代に、主として、言葉でそれをやったのである。彼の実験的といわれる演劇にしても、その発想のもとは、やはり言葉だった。そのような寺山の多彩な活動を、86歳の寺山修司がアイドルを募集するという設定で、往時の彼の活動を模倣・反復しつつ、その行く末までを見事に描き出したのが、中森明夫の小説『TRY48』なので、是非ご一読を。
今回、シネ・ヌーヴォで上映される映画のラインナップを見て、ホーッと感心したのは、東映がらみの『ボクサー』を除いて、短篇までを含めて、ほぼ全作があがっていることだ。なお『草迷宮』では相米慎二が助監督を務めているが、『台風クラブ』の一場面で、寺山の映画に似合いそうな輩が出てくるショットがあるので、そちらのほうも、ご覧下さい。
|
|